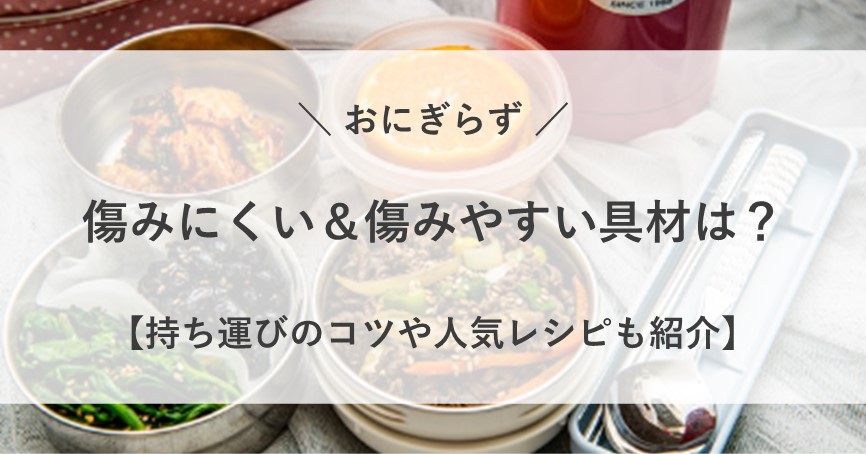お弁当で『おにぎらず』を持ち運ぶ際、特に気になるのがその保存性です。
時間が経過すると傷みやすくなるため、傷みにくい具材を選ぶことが非常に重要です。
加工食品のスパムや缶詰、殺菌効果のある梅干しは、保存性が高く、持ち運びにも適しています。
一般的に、おにぎらずはお弁当として人気があり、完成後しばらく経ってから食べられることが多いです。
特に暑い時期には食中毒のリスクが高まるため、傷みにくい具材を選ぶことがさらに重要になります。
この記事では、おにぎらずに最適な傷みにくい具材を選ぶポイントや、特におすすめの6種類の具材、簡単な作り方と人気レシピを詳しく紹介します。
これらの情報を参考にして、美味しく安全なおにぎらずを作ってみてください。
おにぎらずにオススメの傷みにくい具材6選
おにぎらずに適した傷みにくい具材としては、缶詰めや殺菌効果のある食品がおすすめです。
塩分や調味料が豊富な食材は細菌の増殖を防ぎ、保存性を向上させます。
また、水分を多く含む材料は使用前にしっかりと水気を切ることが重要です。
生の食材は避け、加工品や十分に火を通した食材の使用が推奨されます。
ここで、おにぎらずに最適な傷みにくい具材を6つはこちらです↓
- 加熱殺菌された缶詰の焼き鳥
- 殺菌効果のある食材
- 味付けが濃い食材
- 完全に火を通した食材
- スパムなどの加工食品
- 冷凍のから揚げなど
これらの具材の特徴やメリットに加え、簡単な作り方や人気のレシピもご紹介します♪
加熱殺菌された缶詰の焼き鳥
缶詰の焼き鳥は加熱殺菌されているため、おにぎらずの具材に最適です。
調理が不要で、冷めても美味しいので、おにぎらずの準備が迅速に行えます。
長期保存が可能で家庭での常備にも便利ですし、小さくカットされているため食べやすく、おにぎらずに入れやすいです。
また、しっかりとした味付けがされており、ご飯との相性も良いですよ♪
栄養面でも優れており、腹持ちが良く、たんぱく質の摂取にも役立ちます。

殺菌力がある食材の活用
梅干し・生姜・お酢はそれぞれに殺菌効果があり、おにぎらずに最適です。
これらを細かく刻んでご飯に混ぜることで、その効果を全体に広げることができます。
梅干しを選ぶ際には、塩分が多いタイプが好ましいです。
また、お酢も殺菌効果を持ち、ご飯に少し混ぜて炊くと良いでしょう。
量が少なければ、お酢の味が強くなることはありません。
塩分を多く含む食材
塩分が多い食材は、細菌の増殖を防ぐのに効果的です。
佃煮や塩昆布・きんぴらごぼう・そぼろ・焼肉・生姜焼き・プルコギなどがおすすめです。
これらは、煮汁がなくなるまで煮詰めたり、水分をしっかり取り除いてから使用するのが良いでしょう。
しっかり加熱した食材
卵や鮭なども、十分に加熱することでおにぎらずに適した具材となります。
加熱した卵は他の肉類と組み合わせても美味しく、鮭は忙しい朝でも簡単に調理できて便利です。
加工食品の使用
スパム・ハム・ソーセージ・ちくわなどの加工食品も、適切に加熱することでおにぎらずに良く合います。
特にスパムはフライパンで焼くことで殺菌効果が高まります。
ベーコンやハムなど他の加工食品も同様です。

冷凍食品の利用
カツ・唐揚げ・魚のフライなどの冷凍食品は、おにぎらず作りに手軽でおすすめです。
これらは低温で保存されるため長期間保管可能で、細菌の増殖も心配ありません。
最近の冷凍技術の向上により、味や栄養価を維持することも可能です。
冷凍食品をおにぎらずに入れる際には、しっかりと加熱してから冷まして使用するのが重要です。

美味しくて安心なおにぎらず作りに、ぜひこれらのアイデアを取り入れてみてください♪
おにぎらずの具材で傷みやすい食品
おにぎらずの具材で傷みやすいものは、水分が多く・保存に注意が必要な物で、以下の食材が挙げられます。
- 生の野菜や未加熱の食品
- 水分量の多い食材
- 生たらこや明太子
- 水分を含む調味料(特にマヨネーズ)
たとえば、レタスのような生野菜は見た目を良くしますが、水分が多く、食中毒の原因となることがあります。
また、加熱されていない生たらこや半熟卵などもリスクが高く、特に暑い日の持ち運びには適していません。
おにぎらずに使用する具材は、食中毒のリスクに直接関わるため、慎重な選択が求められます。
おにぎらずを安全に作って持ち運ぶコツ
おにぎらずをお弁当に入れる場合は、素手で作らない・水分を取り除く・温度管理をする(保冷バッグや保冷剤を利用する)ことが効果的です。
食中毒は気温や湿度と密接に関係しており、適切な具材選びと水分の管理が重要となります。
素手で作らない
おにぎらずで食材が傷むのを防ぐために、なるべく直接手で触れないようにすることが一つの重要なポイントです。
おにぎらずに使われる肉・魚・卵・野菜などの食材は、菌が繁殖しやすい特性を持っているため、素手で触れると手の菌が食材に移り、食品の傷みを早める可能性があります。
具材を扱う際は、清潔な手袋の使用をお勧めします。
また、ラップや使い捨てのビニール手袋を利用して触れることも効果的です。
さらに、調理に使用する道具やまな板を常に清潔に保つことも、食品を安全に保つ上で大切です。
水分を取り除く
おにぎらずを作る際の湿度管理は、食中毒のリスクを減らす上で非常に重要です。
具材とごはんはしっかりと冷ました状態で使用しましょう。
暖かい状態でおにぎらずを密封すると、水滴が発生し、その結果、細菌が繁殖しやすくなってしまいます。
また、具材に含まれる水分も細菌の繁殖を促すため、水気をしっかり取り除くことが大切です。
ごはんは平らな皿やバットに広げ、扇風機やうちわなどを使って冷ましましょう。
ただし、ごはんが乾燥しすぎないように気をつけてください。
温度管理をする
食中毒のリスクが高まるのは、気温が30〜40℃の時です。
この温度帯では食品が傷みやすくなります。
黄色ブドウ球菌などは10℃以下で増殖が抑えられるため、おにぎらずを冷やして持ち運ぶことが推奨されます。
保冷バッグや保冷剤を活用し、職場では冷蔵庫への保管を心掛けましょう。
車内での保管には、クーラーボックスや冷凍ペットボトルが有効です。
また、食中毒を防ぐためには、おにぎらずをできるだけ早く食べることも大切です。
さまざまなサイズがある保冷バッグを、お弁当の量に合わせて選ぶのも良いでしょう。
これらの工夫をすることで、美味しく、安全なおにぎらずを持ち運び、楽しいお弁当の時間を過ごすことができます。
おすすめ!簡単おにぎらずレシピ3選
以下に、人気のあるおにぎらずのレシピを3つ選んでみました。
- スパムと卵のおにぎらず
- ツナとマヨネーズのおにぎらず
- 豚肉のしょうが焼き風おにぎらず
これらのレシピはいずれも簡単に作れるので、お忙しい朝や子供と一緒に作るのに適しています。
スパムと卵を使ったおにぎらず
スパムと卵を使ったレシピは、おにぎらずの定番です。簡単に作れておいしいですよ。
材料(2人分)
- ご飯:300g
- 焼き海苔:2枚
- スパム:1.5枚(1cm厚さ)
- 卵:1個
作り方
- スパムを焼き、卵を厚めに焼く。
- ラップの上に海苔を敷き、ご飯、卵、スパム、ご飯を順に重ねる。
- 海苔で包んでラップで固定し、馴染んだら半分に切って完成。
加熱することで持ち運びにも適しています。
ツナマヨを使ったおにぎらず
ツナマヨは、老若男女に愛される人気の味です。しっかり水分を切ることで長持ちします。
材料(2人分)
- ご飯:300g
- 焼き海苔:2枚
- ツナ(シーチキン):80g(1缶)
- マヨネーズ:大さじ1
- 塩:ひとつまみ
- レタス:1〜2枚
作り方
- ボウルでツナ、マヨネーズ、塩を混ぜ合わせ、レタスは水気をしっかり拭き取って大きめにちぎる。
- ラップの上に海苔を敷き、ごはん、レタス、ツナマヨ、ごはんの順に重ねる。
- 海苔で全体を包み、ラップで固定した後、馴染ませてから半分に切って完成。
見た目も鮮やかで、職場のランチやピクニックにも最適です。
豚肉のしょうが焼き風おにぎらず
豚肉を使ったしょうが焼き風のおにぎらずもおすすめです。牛肉や細切れ肉でも代用可能です。
材料(2人分)
- ごはん:300g
- 焼き海苔:2枚
- しょうが焼き用の豚肉
- レタス:1〜2枚
- マヨネーズ:適量
- すき焼きのタレ:大さじ2
作り方
- 豚肉を焼き、すき焼きのタレで味付け後、水分を飛ばす。
- ラップの上に海苔を敷き、ごはん、レタス、豚肉、マヨネーズ、レタス、ごはんの順に重ねる。
- 海苔で包んでラップで固定し、馴染ませたら半分に切って完成。
ボリュームたっぷりで、栄養バランスも良く、持ち運びにも便利です。
これらのレシピで、お手軽に美味しいおにぎらずを作ってみてください♪
手軽に作れるおにぎらずの作り方
誰でも簡単にできる『おにぎらず』の作り方をご案内します。
おにぎらずは作り方が簡単で、見た目も楽しいので、子供たちとの料理時間にも最適です♪
また、食品安全性を考え、腐りにくい具材の選択が大切です。
おにぎらずの手順
- ラップを敷く:ラップを使うことで、細菌の増殖を防ぎます。
- 海苔を置く:ラップに海苔を置きます。海苔の角が上に来るようにしてください。
- ご飯をのせる:海苔の中央に四角い形でご飯をのせます。食べやすい量に調整しましょう。
- 具材を追加:ご飯の上に具材をのせ、その上に再びご飯を加えます。具とご飯のバランスに注意してください。
- 海苔で包む:海苔の四隅を中心に向かって折り、ご飯と具を包み込みます。
- 海苔とご飯をなじませる:ラップで包んで少し置くことで、海苔とご飯がなじみます。
- 切り分ける:海苔が柔らかくなったら、ラップごとおにぎらずを中央から包丁でカットします。
切る際には、包丁を水で濡らすとキレイに切れます!
これらのステップに従えば、彩り豊かで美味しいおにぎらずが簡単に作れます。
海苔を敷いて、ご飯と具材を重ね、パッと海苔で包んで切るだけのシンプルな方法ですので、子供たちも手伝いやすく、一緒に楽しく作ることができます。
おにぎらず作りに役立つ便利アイテム
おにぎらずを作る際に役立つアイテムを見ていきましょう。
作るのが簡単な『おにぎらず』ですが、便利アイテムを使う事で、形がキレイなおにぎらずが、素早く簡単に作れるようになります♪
パール金属:おにぎらず Cube Box
このおにぎらず型は、ご飯が付きにくい特別な加工が施されていて、簡単におにぎらずを作ることが可能です。
さらに、様々なレシピが試せる9種類のレシピカードも付属していて便利ですよ!
カラーバリエーションは白・赤・ブラウンの3色展開で、大きいサイズと標準サイズが選べます。
どのサイズも均一な形で美しいおにぎらずが作れるので、好みに合わせてお選びいただけます。
おにぎらパ(Onigirapa)
次にご紹介するのは、作ったおにぎらずをそのまま携帯できるおにぎりケースです。
このケースを使えば、ラップの必要がなく、手も汚れずにサッとおにぎらずが作れます。
また、作ったそのままで持ち運べるので、時間を節約し、洗い物も減らせます。
繰り返し洗って使用できるため、衛生的で経済的な選択肢となります。
これらのアイテムを使うことで、おにぎらず作りがさらに簡単で楽しい時間になるでしょう♪
安全で美味しいおにぎらずの具材と作り方のポイント
この記事では『おにぎらずの傷みにくい具6選』『傷みやすい食材』『持ち運びのコツや人気レシピ』を紹介しました。
傷みにくい具材は『缶詰めや殺菌効果のある食品』で、
- 加熱殺菌された缶詰の焼き鳥
- 殺菌効果のある食材
- 味付けが濃い食材
- 完全に火を通した食材
- スパムなどの加工食品
- 冷凍のから揚げ
などがおすすめです。
傷みやすい具材は、生の野菜や未加熱の食品・水分量の多い食材・生たらこや明太子・水分を含む調味料(特にマヨネーズ)です。
おにぎらずをお弁当に入れる場合は、素手で作らない・水分を取り除く・温度管理をする(保冷バッグや保冷剤を利用する)ことが効果的です。
おにぎらずは、さまざまな具材を組み合わせることで多彩な味わいを楽しめ、お弁当やパーティー、おもてなしにもぴったりです。
適切な具材を選んで、美味しくて安全なおにぎらずを作り、楽しい食事の時間をお過ごしください♪
-
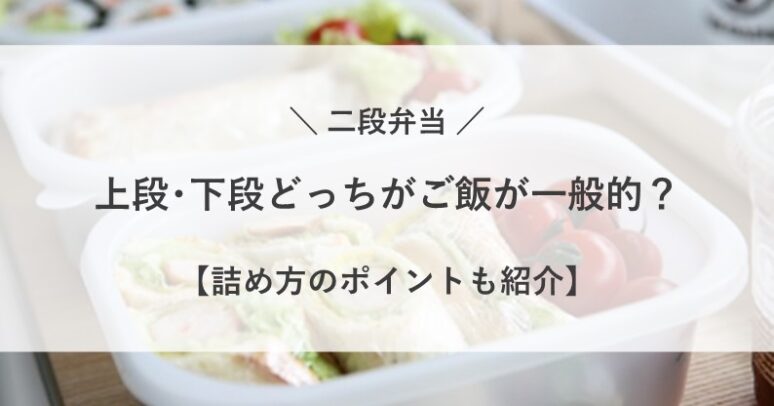
-
参考二段弁当はどっちがご飯が一般的?男女別の詰め方のポイントも紹介
続きを見る